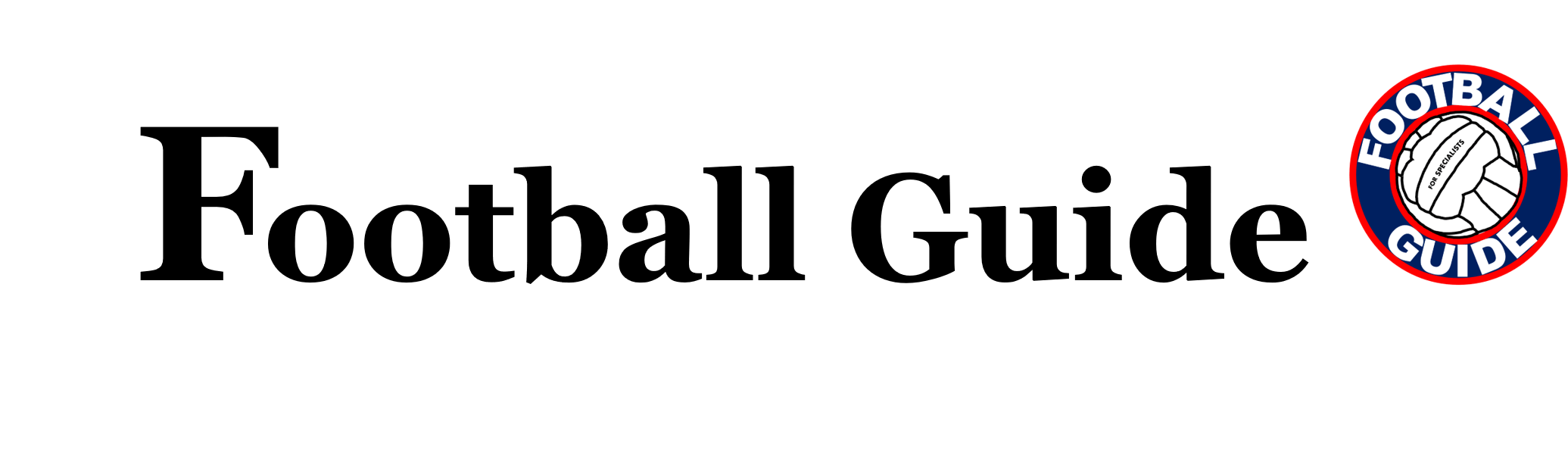戦術というものは、指導チームやクラブ全体を健全に成長させる手段のほんの小さな一カテゴリーにすぎません。
他の記事を読んでいただいている方はご存じかと思いますが、組織の健全な構築や再建には様々なアプローチが必要になります。
指導を生業にしている皆様には釈迦に説法ですが、指導者にとってゲーム戦術とはその指導者にとっての「技術」の一分野、あるいは成功のための一手段に過ぎず、この理解力や採択能力が低くても強いチームは作れます。
実際に私はロンドンのユース世代、アイルランドの名門セミプロクラブのファーストチーム、日本では高校と大学の両方のサッカー界で指導経験がありますが、世間的には有名なチームでも、その戦い方は観る者から観れば魅力に乏しいチームというものにいくつか出会ってきました。
反対に世間的には無名でもその戦い方に組織の哲学が反映されていて、観る者に感心と喜びを与えるチームにもたくさん出会ってきました。
ところで、そもそもサッカーにおける正義とは何でしょうか?
ゲームに勝利することでしょうか?
負けても観ていて楽しいサッカーをすることでしょうか?
やっていて楽しいサッカーをすることでしょうか?
よくプロ選手からも「プロなので勝ちにこだわりたい」というセリフを聞くことがあります。
しかしながら子どもでも、いえ、子どもの方が勝利というものを切望し、例えばジャンケン一つでも一手入魂かのように大声を上げながら力を込めてグーチョキパーを出します。
ジャンケンでこれですからスポーツの試合では大変です。
ズルをしたり、時にはラフプレーに頼ったりします。
勝ちにこだわっています。
そして負けた時も大変です。
大泣きします。
勝ちを切望しています。
プロの指導者やその年代に近い、あるいはその可能性を秘めたタレントを持つ選手たちを指導する指導者たちはどうあるべきでしょうか?
言うまでもなく、世界にサッカーほど注目度が高く競技人口、観戦人口が多いスポーツはありません。
誤解を恐れずに言えば、他のスポーツに比べて発信力と影響力が圧倒的に大きいということです。
そのサッカーにおいて「まず勝つこと」を目標に設定した場合、受信する側、影響を受ける側はどうなるでしょうか?
あるいは同じチーム内でも、そのような価値観を強いられる側(選手)はどのような人間に育つでしょうか?
その答えの代わりに、良くも悪くもこれまでにFIFAが施策してきたことをヒントにサッカーの正義について考えてみましょう。
FIFAが下す判断や決定事項が現場の人間に直接的に関わってくるものの一つに、ゲームルールの変更があります。
そのルール変更の歴史一つを紐解いてもいかに攻撃側が優遇されてきたかが分かります。
そこにはふんだんに商業的な理由が隠されていますが、(攻撃側が優遇されたおかげで)「得点がたくさん入るスポーツの方がお金を設けられる」ということは、言い換えれば「得点をたくさん取ること」、少なくとも「得点を取るために積極的になること、努力すること」はファンを増やすことが出来る、つまりそういう試合やスポーツそのものが人々を喜ばせることができる、ということになります。
世界各国国民性の違いがあるので普遍的にこれが正解とは言えませんが、国際サッカー連盟が判断した基準には間違いなく攻撃サッカーの方が大多数に受けるという考えがあったことでしょう。
「プロなので勝ちにこだわりたい」
サポーターは勝利のみを望んでいるわけではありません。
勝ち負けのみで興奮できて一喜一憂したいなら、大袈裟な話、人々の娯楽にスポーツは必要なく、ジャンケンだけがあればいいわけです。
また勝利至上主義の経済社会で生きている我々人間にとって、実社会から離れられるスポーツまでもがその流儀で行われていると、特にサポートしているチームが負けた場合には日々の鬱憤の出口をそのスポーツに見つけることが難しくなります。
スポーツはやる側にも観る側にもカタルシスや心の開放が求められます。
サッカー指導にかかわらず教育業というものは使命感を持ちやすい活動でありますが、特に我々サッカー人は地球上最も多くの人々を熱狂させているスポーツの関係者であることを自負しなくてはいけません。
繰り返しになりますが、他の活動に比べて影響力が大きいということです。
たかがサッカー、されどサッカー。
そして勝つために、あるいは勝ち負け以前に自分達が意図したことを出来るだけ多く、長く、ピッチ上で表現するには、戦術の理解が必要になります。
つまり成功の一手段にしか過ぎない戦術も「されど」戦術であります。
※「専門家のサッカー解説書 Foundation」より抜粋